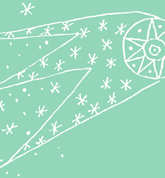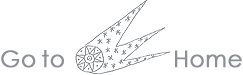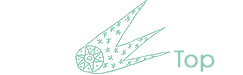|
詩人の岸田衿子さんの北軽井沢の別荘に、遊びに出かけたことがある。 私の名前は岸田さんの「エリコ」からいただいたものだし、彼女の美しい作品世界に潜む恐さや残酷さには、前々から魅せられていた。 なにか珍しい面白がれるものをと、私は手土産に、チョコレートの消しゴムの詰め合わせを1箱買い、赤いリボンをかけた。 夏休みの静かな午後。 涼しげな風の渡る居間の木のテーブルの上で、衿子さんが包みを開くと、ぷーんと甘い香りがあたりに広がった。 色も形も大きさも、本物と見分けがつかない。柔らかで弾力ある上等のチョコレートといったふうである。 「まあ、嬉しいわ。ちょうどおやつにしようと思ってたところなの。今、紅茶をいれるわね」 衿子さんはいそいそと、台所に立つ。 なんだか、おかしくてたまらない。 うつむいて、私は笑いをかみころす。子供たちや編集者など、6人ほどが集まっているのに、誰もそのお菓子がニセモノだと気付かないのだ。 
ほんの冗談のつもりだったから、すぐにネタばらしをする予定でいた。 けれど、喜んではしゃぎまわる子供たちの相手をしているうちに、機会を逸してしまった。 さわさわと、木立が揺れる。 やがて、湯気のたつティー・カップが配られた。 「それじゃ、いただきましょう」 と、衿子さんの手が伸びたとき、私はあわてて身を乗りだした。 「あのうー」 ところが、なんというタイミングだろう。 ピンポーンという玄関のチャイムの音に、私の声はかき消された。 お隣の大学教授が訪ねてきたのだった。 銀ぶち眼鏡の温厚そうな顔が、居間にあらわれた。 「ほほう、これはいいところにやってきましたな。私は、チョコレートが大好物でしてね」 「枝里子さんが持ってきてくださったんですよ。宜しかったら、ご一緒にどうぞ」 と衿子さんが誘う。 では遠慮なく、と教授は輪の中に入ってきた。 (これは、まずいことになったゾ) 私は見知らぬ人から目を離せずにいる。彼は、無雑作に腕をのばし、チョコレートをひとつ、つまんで口元に持ってきた。 「あのうー」 意を決し、再び私が声を発したちょうどそのとき、彼は、おや、という表情で、手を止めた。 私はほっと胸をなでおろした。 「なんだ、これ、消しゴムじゃないか」 そんな一言が飛びだすにちがいなかった。 私はじっと待った。 しかし ―― 意外にも、白いものが半分混じった頭をかきながら、彼はこう言ったのである。 「ちょっと大きすぎるようですな。どうもこのところ歯を弱くしまして‥‥。すみません、ナイフをお借りできませんかね」 衿子さんが果物ナイフを手渡した。 (うーん。ま、切ってみれば、いくらなんでも気付くはずよね) 私は青ざめ、手にじっとりと汗をかいている。 教授は丁寧に、チョコレートを半分に割った。 あれ?まだ、わからないの?! 「あのうー」 三度、声をかけたが、間に合わなかった。 教授は何のためらいもなく、チョコレートをひとかけら、ぽーんと口に放りこみ、次の瞬間、顔をゆがめながら、歯型のついた茶色の塊を吐き出したのだった。 爆笑の渦の中で、私ひとり、平謝りにあやまったのは言うまでもない。 チョコレートの消しゴムを手にすると、林を抜ける風の色と、衿子さんの笑い声が甦る。 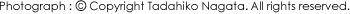 |